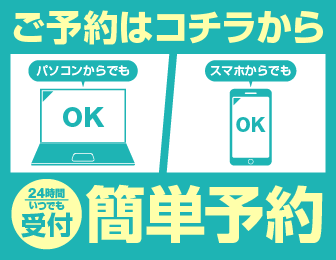海外支援活動①:パラオへ 医療を考える

今回、1週間のお休みをいただきパラオでの医療支援活動「Pansy Project」に初めて参加してきました。

Pansy Projectとは7年前から活動しているNPO団体で、以前よりお誘いをいただいていたのと、色々な思いがあり意を決して今回参加させてもらいました。
前から話を聞くたびに「いつか行ってみたい」と思っていましたが、実際に自分が現地に立つと、想像していた“海外医療”とはまったく違う世界が待っていました。
まずは出発から。
成田空港を朝10時に飛び立ち、グアム経由でパラオへ。


到着は深夜1時。なかなか長い旅です。
空港に着いた瞬間、むわっとした湿気と南国の匂いが一気に押し寄せてきて、「ああ、本当に来たんだな」という実感が湧きました。
ホテルに着いたときは真っ暗。

街灯も少なくて、海の音だけがかすかに聞こえる静かな夜でした。
翌朝外に出ると、いきなり太陽が高い位置にあって驚きました。

ガイドさんによると パラオの日差しは日本の7倍ほど強い らしく、本当に肌がじりじりと焼けるようでした。
ここで少しパラオについて補足します。
パラオは大阪の真南あたりに位置し、時差はゼロ。
日本から行きやすい南国ですが、観光だけでなく、
ダイビングの世界では「セブ・モルディブと並ぶ三大スポット」に挙げられる国でもあります。
今回の滞在中も、あちこちでダイバーの姿を見かけました。


こんな写真がいたるところでいとも簡単に撮れてしまいます。
国全体は 大小500以上の島 で構成されていて、人口は約1.8万人。
世界でも屈指の“小さな独立国”です。
道路は右側通行、信号はほとんどなし。
夜は早く、20時を過ぎると街全体が静かになる。
その代わり、昼間は陽の光と海の青さが本当に鮮やかで、時間の流れそのものがゆっくりしています。
経済状況はかなり特徴的です。
平均月収は約500ドル(約8万円)。
観光業や漁業が主産業で、物価は意外と高い。
特に野菜は輸入頼みなので高額で、冷凍食品や缶詰が多くなりやすい。

野菜のコーナーもこんな感じで、

お肉は冷凍ですね。


砂糖を使った甘い飲み物やお菓子も多く、砂糖の摂取量が多い=虫歯のリスクが高いという背景があります。
成人の生活習慣病(特に糖尿病)が多い理由も、食生活と運動不足が絡んでいます。
そうそう、地元の小学生にサッカーに混じらせてもらいました。
サッカーはどこでやってもサッカーですね。
無尽蔵の体力の子供たちに打ちのめされる前の写真です。

その中で、今回の活動の中心となったのが ベラウ国立病院(Belau National Hospital)。

パラオの医療の中心で、歯科もここがメインです。
現地の人員は、歯科医師2名、歯科衛生士4名、歯科助手2名、歯科技工士2名。
この人数で島全体を診ていると考えると、本当に大変です。
実際、設備は常にギリギリ。
ユニットは5台ありますが、水が出にくかったり、ライトが暗かったり、バーが折れたり。

デジタルのデンタルレントゲンはギリギリ動くものの、パノラマレントゲンは故障して長期間放置されていて使えない状態でした。
その一方で、機材には「From the People of Japan」と書かれたステッカーが貼られているものも多く、日本からの支援が大きかったことも感じられました。
ただ、それを扱いきれる体制がない。
ここは後半の“支援の話”にもつながっていきます。
診療初日は、自己紹介からスタートしました。

英語は問題なく通じるわけではないですが、現地スタッフはすごくフレンドリーで、笑顔やジェスチャーで十分伝わります。
こういうところに、パラオの人の「優しさ」「ゆったりした気質」を強く感じます。
実際の診療が始まると、日本との圧倒的な違いがすぐに見えてきます。

ほとんどの患者さんの目的は “痛みを取ること” のみ。
理由はシンプルです。
-
治療費が高い(抜歯8ドル、根治・CRは100〜400ドル)
-
歯科医院が3軒しかない
-
予約は3ヶ月後
-
そもそも「今日しか来れない」
日本のように「保存できる歯は残す」という前提がありません。
今日痛いなら今日抜く。
それが彼らにとっての合理的な選択です。
最初に診た患者さんは頬の痛みを訴えていて、進行した虫歯が原因でした。
日本なら根管治療で保存、という判断もできますが、
彼は迷いなく「抜歯でお願いします」と言いました。
処置後、
「これで今日から眠れる。ありがとう」


と言われた言葉は、本当に重かったです。
普段、日本で「歯を残す」ことばかり考えている立場として、
“痛みを取りたいだけ”という価値観は、理解しつつも衝撃的でした。
でも、彼らの生活背景を知ると、それが自然に感じられます。
働き方も不安定で、日々の生活で歯の治療に時間とお金をかけられない。
歯科にかかる“ハードル”がとても高いんです。
昼休みには外へ出て、海を見ながらお弁当を食べました。

差し入れのココナッツをみんなで飲んだりしながら、
「医療って、本来はこういうシンプルな形だったのかもしれない」と思えてきます。
現地スタッフとは日を追うごとに仲良くなってきて、
治療中も自然と連携が取れるようになりました。

言葉が完璧じゃなくても、誠意と気持ちで十分に伝わる。
それを強く実感しました。
こうしてパラオで過ごした1日目を終えた時点で、
すでに “医療の原点” を考え始めていました。
日本では、
設備・技術・制度・説明義務・予約管理・保険制度……
あらゆる要素が複雑に絡んでいます。
しかしパラオでは、
目の前の患者さんの痛みを取り、その日を安心して過ごしてもらうこと。
それだけが医療の中心にあります。
この“シンプルさ”の中に、
医療の大事な部分があるのだと、強く感じました。
次回は、滞在中に訪れた ペリリュー島 の話を書きます。
ここは太平洋戦争の激戦地。

“命を奪う行為”と“命を守る医療”を対比して考える時間になりました。