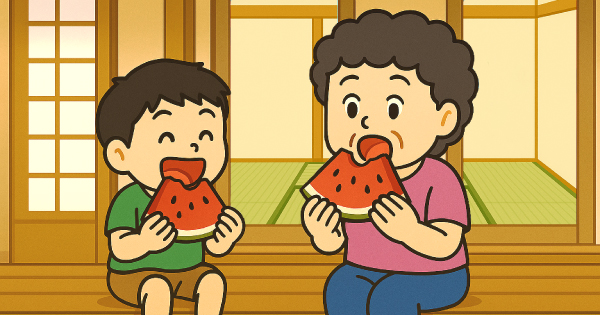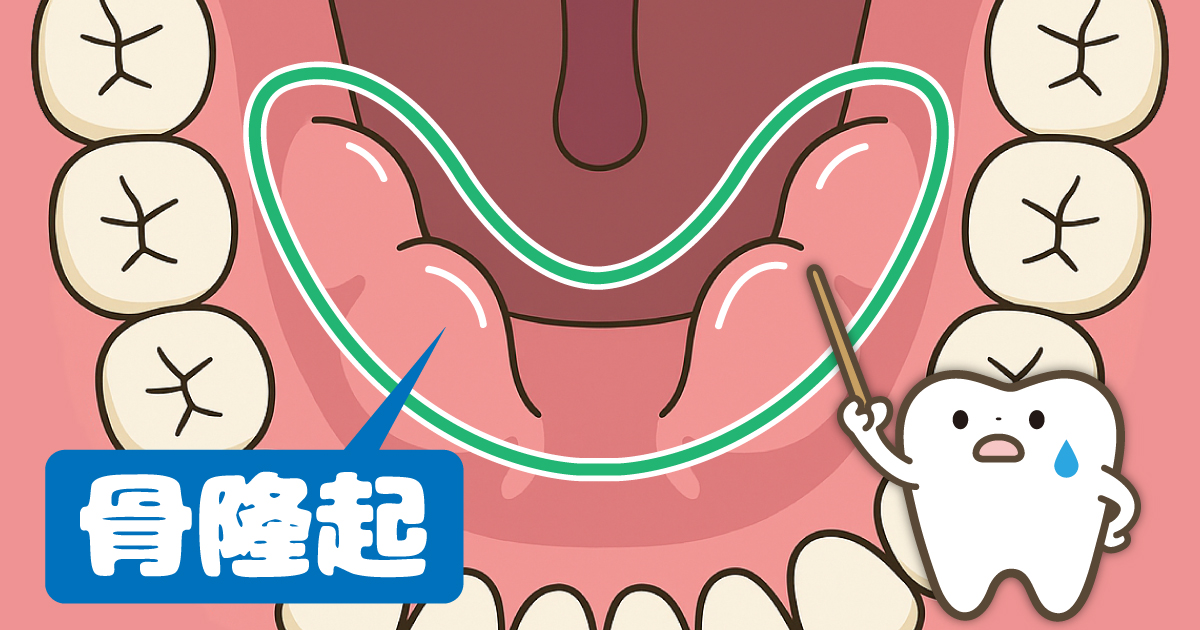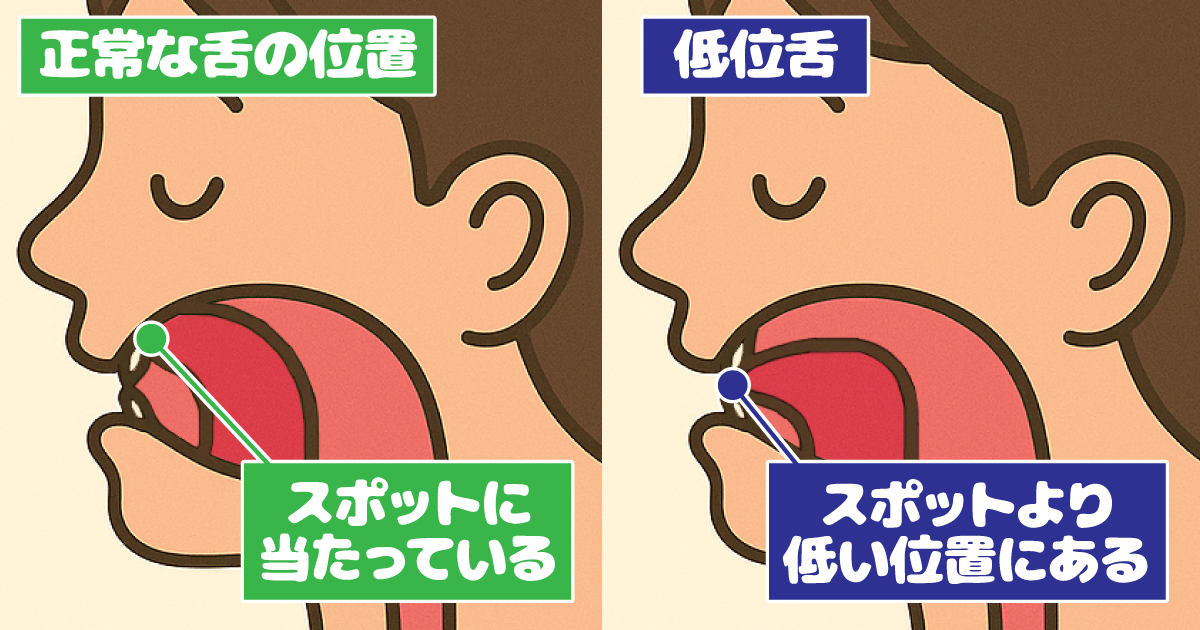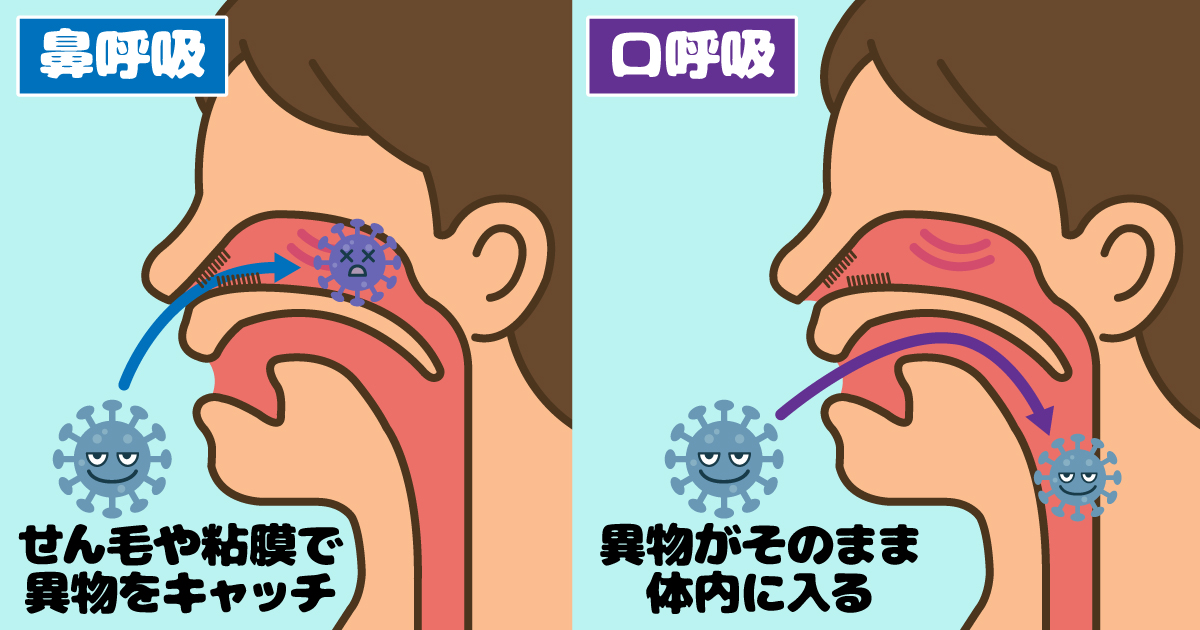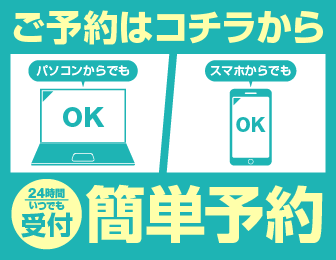石垣島に慰安旅行へ
こんにちは。院長の和田です。
本格的な夏を迎え、うだるような暑さが続いていますが、皆さま夏バテなどされていませんでしょうか。
夏バテで免疫力が低下すると歯周病などのお口のトラブルも増加してしまいます。
体調管理にはくれぐれも気をつけて、暑い夏を乗り切りましょう。
さて、先月の6⽉30⽇から7⽉2⽇まで、2泊3日で石垣島の「クラブメッド 石垣島 カビラ」を訪れました。


当院スタッフとの慰安旅行です。
クラブメッドはさまざまの国で展開しているそうで、アクティビティやレストランなども包括されていました。
そこで今回は、ゆったりと景色を楽しむ旅というよりも、リゾート内のアクティビティを存分に楽しんできました。
現地では、お店はどこにしよう、料金も調べて…といった煩わしさもなく、思い切り楽しむことができました。

海やプール、マウンテンバイクに空中ブランコ、スノーケリングにヨガと盛りだくさん。
ほかにも夜の星空、バイキングでの食事も満喫してきました。
また、併設されているバーでは、普段はあまりとれないゆっくりした時間の中、会話を楽しむことができました。

日々の診療に、ひたむきに向き合っているスタッフたち。
お互いの頑張りを一番近くで見ている仲だからこそ、労いあう意味でも有意義な旅となりました。
息抜きもでき、より深まった親交で日々の診療を頑張りたいと思います!

WADA DENTAL CLINIC
〒816-0941
福岡県大野城市東大利2-2-6
TEL:092-571-5240
URL:https://wada-dental-clinic.jp/
Googleマップ:https://maps.app.goo.gl/5ARDH8MLhieFE4F67